人事担当者向け
【キャリアオーナーシップ】”じりつ”した社会人の本質
2025.08.19
キャリアオーナーシップとは
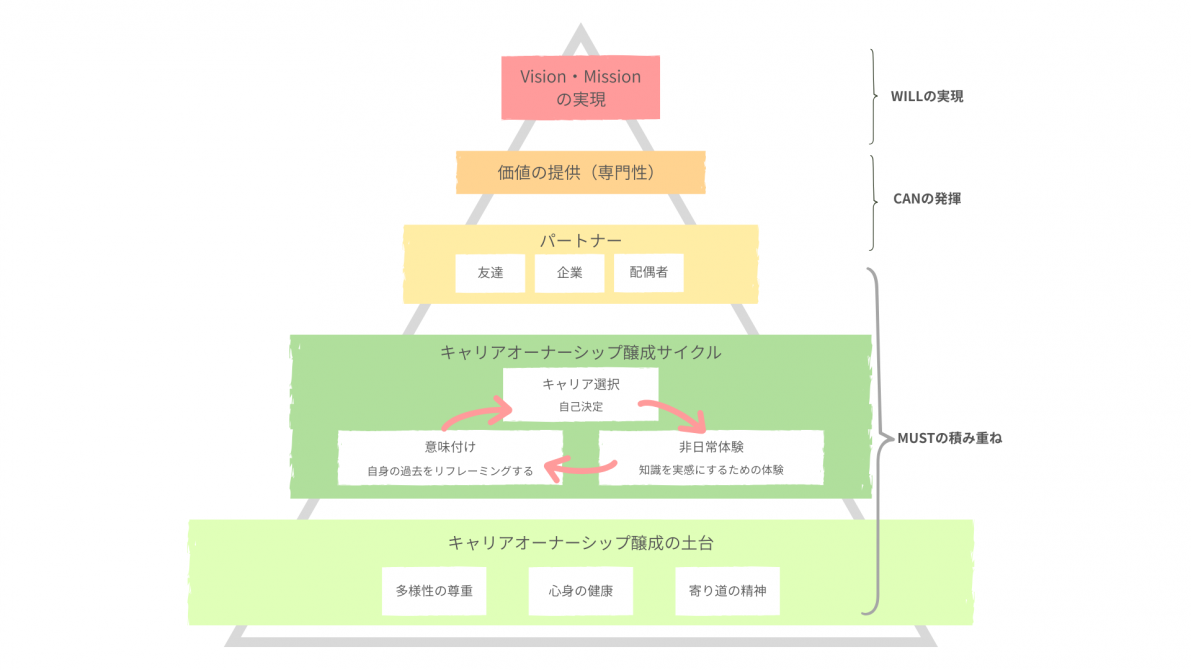
キャリアオーナーシップは、自分のキャリア(仕事だけではなく、時間の使い方)を責任持って決められる力を自分自身が握っていると実感できることです。これは社会人になる前の学生だけではなく、ベテランになっても、企業を定年退職しても、経営者であっても必要なことです。
自分の選択に責任を持つこと。自分の意思で選択することは、幸せに生きる一要素と言えます。キャリアオーナーシップをライフステージごとに考えてみましょう。
参考リンク:【須田コラム】自己決定と幸福度
ライフステージ別キャリアオーナシップ
高校卒業者
高校卒業者は、自身のキャリアパスを決定する上で重要な岐路に立たされています。大学進学、専門学校への進学、就職など、様々な選択肢の中から自分に合った道を選ぶ必要があります。その際、親や先生など影響を受ける対象が非常に狭いことが問題です。
この段階でのキャリアオーナーシップは、以下の点を意識することから始まります。
- 主体的な意思決定: 親や教師、友人の意見も参考にしつつ、最終的な決断は自分自身で行うという意識を持つことが重要です。自分の人生の責任は自分にあるという感覚が、キャリアオーナーシップの根幹をなします。
- 変化への適応: 現代社会は変化が速く、一度決めたキャリアパスが常に最善であるとは限りません。状況の変化に応じて柔軟に対応し、必要であれば進路や職種を見直す勇気もキャリアオーナーシップの一部です。
- 学び方と目標設定: 学習の方法と同様に仕事の覚え方や新しい資格やスキルなど学び方を学ぶ意識を持ちます。そのためには何を目指すのかどんな指標があるのかなど目標設定を自分ですることを練習しましょう。
- 選択肢は無限: 自身の視野が狭いことや限られた範囲の中の価値観であることを知ります。この世の中には知らないことがまだまだあるということを受け入れ、高卒時の選択は変更可能であるということを知ります。
高校卒業時点でのキャリアオーナーシップは、将来の基盤を築く上で非常に重要であり、早い段階から自身のキャリアに主体的に関わる姿勢を養うことが求められます。
大学卒業者
大学卒業者は、より専門的な知識やスキルを身につけ、多様なキャリアパスを選択する機会に恵まれています。この段階でのキャリアオーナーシップは、以下の点を意識することが重要です。
- 専門性の追求と汎用スキルの習得: 大学で得た専門知識を深めるだけでなく、どのような職種でも役立つ汎用的なスキル(問題解決能力、コミュニケーション能力、論理的思考力など)を積極的に習得することが重要です。
- キャリアの選択肢の広がり: 就職、大学院進学、起業、フリーランスなど、高校卒業時よりも多くの選択肢があります。それぞれの選択肢のメリット・デメリットを理解し、自身の価値観や目標に合致するかを検討する必要があります。
- 継続的な学習と自己成長: 変化の速い現代社会において、一度身につけた知識やスキルが陳腐化する可能性もあります。常に新しい情報を学び、自己を更新していく姿勢がキャリアオーナーシップを支えます。
- ネットワークの構築: 大学内外の多様な人々とのつながりを大切にし、情報交換や意見交換を行うことで、新たな視点や機会を発見できることがあります。メンターを見つけ、キャリア形成に関するアドバイスを得ることも有効です。
大学卒業時点でのキャリアオーナーシップは、社会人としての自立と成長の基盤を築く上で極めて重要であり、自身のキャリアを能動的に形成していく姿勢が求められます。
20代の社会人
20代の社会人は、キャリアの基盤を築き、将来の方向性を見定める重要な時期です。この段階でのキャリアオーナーシップは、以下の点を意識することが求められます。
- 自己分析とキャリアビジョンの明確化: これまでの経験を振り返り、自分の得意なこと、苦手なこと、情熱を傾けられること、将来どうなりたいかを具体的に考えることが重要です。短期・中期的な目標を設定し、それに向けた行動計画を立てます。
- 主体的なジョブローテーションや異動の希望: 会社に与えられた役割をこなすだけでなく、自身のキャリアプランに沿って、異なる部署での経験や新たな業務への挑戦を積極的に希望することもキャリアオーナーシップの一環です。
- 社内外のネットワーク構築: 所属する企業内だけでなく、異業種交流会やセミナーなどを通じて社外の人脈を広げます。多様な価値観に触れ、新たな情報や機会を得ることで、自身のキャリアの選択肢を広げます。
- ワークライフバランスの追求: 仕事だけでなく、プライベートの時間も充実させることで、心身ともに健康な状態を保ち、長期的なキャリア形成を可能にします。趣味や自己啓発に時間を使うことも重要です。
- 失敗からの学びと成長: 20代は様々な挑戦ができる時期でもあります。失敗を恐れずに新しいことに取り組み、たとえうまくいかなくても、そこから学びを得て次に活かす姿勢が、キャリアオーナーシップを育みます。
20代の社会人にとってキャリアオーナーシップは、変化の激しい現代社会で自律的にキャリアを築き、持続的な成長を遂げるために不可欠な考え方です。主体的にキャリアと向き合い、自らの意思で道を切り開いていく姿勢が求められます。
ベテラン社会人
ベテラン社会人は、長年の経験と実績を積んでおり、キャリアの集大成に向かう時期です。この段階でのキャリアオーナーシップは、以下の点を意識することが求められます。
- 経験の棚卸しと再定義: これまでのキャリアで培ってきた知識、スキル、経験を客観的に見つめ直し、自身の強みや貢献できる価値を明確にします。過去の成功体験だけでなく、失敗から学んだことも含めて、自身のキャリアをストーリーとして語れるように整理します。
- 役割の変化と社会貢献: 若手社員の育成やメンターとしての役割を担うことで、自身の経験を次世代に還元し、組織や社会に貢献することを意識します。自身の専門性を活かし、社内外で新たなプロジェクトを立ち上げたり、NPO活動に参加したりすることも含まれます。
- セカンドキャリアの検討: 定年後のキャリアや働き方について、早期に検討を開始します。再雇用、独立、ボランティア活動、地域貢献など、多様な選択肢の中から、自身のライフプランや価値観に合った道を探ります。必要であれば、新たな知識やスキルの習得にも取り組みます。
- 健康とウェルビーイングの維持: 長期的なキャリアを継続するためには、心身の健康が不可欠です。適切な休息、運動、趣味の時間を確保し、ストレスマネジメントを行うことで、充実した日々を送ることを目指します。
- 持続的な学習と情報更新: 変化の激しい現代社会において、常に新しい情報を取り入れ、学び続ける姿勢が重要です。自身の専門分野にとどまらず、幅広い分野に関心を持ち、知的好奇心を満たすことで、新たな可能性を発見できます。
ベテラン社会人にとってキャリアオーナーシップは、これまでの経験を活かしつつ、自身のキャリアを主体的に再構築し、人生の最終章を豊かにするための羅針盤となります。
退職者のキャリアオーナーシップ
退職者にとってのキャリアオーナーシップは、これまでの職業人生で培った経験やスキルを活かし、定年という区切りを超えて、自身の人生を主体的にデザインし、新たな価値を創造していくことにあります。これは、単なる「余生」ではなく、これまでのキャリアの集大成と、これからの人生を能動的に形成していくための重要な概念です。
- 経験の再評価と新たな可能性の探求: 長年にわたる職業経験で得た知識、スキル、人脈を改めて棚卸しし、それが社会や地域、あるいは自身の新たな活動においてどのように活かせるかを再評価します。現役時代の役割にとらわれず、新たな分野への挑戦や学びの機会を探求することも重要です。
- セカンドキャリアの明確化と計画: 退職後の人生をどのように過ごしたいのか、具体的なビジョンを描きます。再就職、独立、ボランティア活動、地域貢献、趣味の深化、家族との時間など、多様な選択肢の中から自身の価値観やライフプランに合った道を検討し、それに向けて具体的な計画を立てます。
- 社会とのつながりの維持・構築: 退職後も社会との接点を持ち続けることは、精神的な健康維持にも繋がります。これまでの人脈を大切にしつつ、新たなコミュニティへの参加や、生涯学習の場を通じて、多様な人々との交流を積極的に行います。
- 健康管理とウェルビーイング: 長期的な視点でキャリアを継続するためには、心身の健康が基盤となります。規則正しい生活習慣、適度な運動、バランスの取れた食事、ストレスマネジメントを意識し、充実した日々を送るための自己管理を徹底します。
- 学び直しと情報収集: 社会の変化は早く、現役時代に培った知識が常に最新であるとは限りません。興味のある分野やセカンドキャリアに役立つ知識について、積極的に学び直す姿勢が重要です。セミナーへの参加、書籍やオンラインコンテンツでの学習などを通じて、常に新しい情報を取り入れるようにします。
- 役割の変化への適応: 現役時代の組織における役割から解放され、新たな役割を自分自身で見つけ出すことが求められます。家族の中での役割、地域社会での役割、あるいは自身の趣味や関心事を通じた役割など、多角的な視点で自己の存在意義を見出し、柔軟に適応していくことが重要です。
退職後の人生は、これまでの経験を土台としつつも、新たな学びや挑戦の機会に満ちています。キャリアオーナーシップの意識を持つことで、退職者は自身の人生をより豊かで意味のあるものにすることができます。
経営者のキャリアオーナーシップ
経営者にとってのキャリアオーナーシップは、自身の企業や事業の成長だけでなく、経営者自身の人生における多様な側面(事業、自己成長、社会貢献、プライベートなど)を主体的にデザインし、責任を持って選択・形成していくことを指します。これは、単に事業を成功させることにとどまらず、経営者自身の存在意義や生き方を深く追求するプロセスでもあります。特に地方の中小企業の経営者は、起業したのか、事業承継したのかでマインドが大きく異なります。
- ビジョンの再構築とパーパスの明確化: 企業のビジョンと自身の人生のビジョンを重ね合わせ、経営者として何を成し遂げたいのか、どのような価値を社会に提供したいのかというパーパス(存在意義)を明確にすることが重要です。事業の成長だけでなく、経営者個人の成長や幸福に繋がるビジョンを描きます。
- 事業と自己成長の統合: 事業活動を通じて得られる学びや経験を、自身の人間的成長やスキルアップに繋げます。また、自己成長のために、新たな知識やスキルの習得(例:最新の経営戦略、テクノロジー、リーダーシップ論など)に積極的に投資し、事業に還元していく姿勢が求められます。
- リスクマネジメントと意思決定: 経営者は常に不確実な状況下で、多くのリスクを負いながら意思決定を行います。キャリアオーナーシップの観点からは、これらのリスクを客観的に評価し、自身の価値観やビジョンに基づいて主体的に判断を下す能力が重要です。失敗からも学び、次へと活かすレジリエンスも不可欠です。
- 多様なステークホルダーとの関係構築: 従業員、顧客、取引先、株主、地域社会など、多様なステークホルダーとの良好な関係を築き、持続可能な事業運営を目指します。経営者自身のキャリアオーナーシップは、これらの関係性を通じて企業の成長と社会貢献を実現する基盤となります。
- ワークライフハーモニーの追求: 経営者は多忙な日々を送りがちですが、自身の心身の健康とプライベートの充実も、長期的なキャリアオーナーシップを支える上で不可欠です。仕事と生活の調和を図り、趣味や家族との時間を大切にすることで、精神的な安定と創造性を維持します。
- 後継者育成と事業承継: 自身のキャリアの最終章を見据え、後継者の育成や事業承継について早期に計画を立てることも、経営者のキャリアオーナーシップの重要な側面です。自身が築き上げてきたものを次世代に引き継ぎ、持続的な発展を可能にするための戦略的な視点が求められます。
経営者にとってキャリアオーナーシップは、事業の成功と自身の人生の充実を両立させ、社会に大きな影響を与えるための羅針盤となります。主体的に自身のキャリアと向き合い、変化の激しい時代を乗り越えるための強い意志と柔軟性が求められます。
”じりつ”した社会人とは何か
ここからは「じりつ(自立・自律)」と「社会人」について考えてみましょう。これらはキャリアオーナーシップと密接に関係しています。
「社会人」とは
「社会人」という言葉は、一般的に学校を卒業し、労働に従事する人を指します。しかし、「学生だって社会に生きている。子どもだって社会の一員である」と言う考えもあるでしょう。広義では、社会の構成員として、経済活動だけでなく、地域活動やボランティア活動など、様々な形で社会に関与する全ての人を指すこともあります。
ではなぜ、学校を卒業し、就職や起業をして労働に従事する人を社会人と呼ぶのでしょうか。英語では社会人を意味する言葉がそもそもありません。ともすると日本独自の価値観における分類なのかもしれません。
ここからは持論となりますが、「社会の維持、存続に貢献している人」という意味が含まれるのではと思っています。そこには単に働いているというだけでなく、社会の一員としての自覚や責任を持つことが求められます。つまり、自分のことだけではなく、他人のことまで責任が持てるようになることのように思います。
「じりつ」とは
似たような言葉に「自立・自律」があります。
「自立」と「自律」は、どちらも「自分を律する」という意味合いを含みますが、その焦点が異なります。
- 自立:他者の援助や支配なしに、自分の力で物事をなすこと。経済的な独立、精神的な独立など、外部からの影響を受けずに自身で立つことを指します。
- 自律:自分自身の規範や価値観に基づいて行動すること。外部からの指示や強制ではなく、自身の意思で判断し、行動することに重きを置きます。
つまり、「自立」は「誰にも頼らずに生きていけること」に近く、「自律」は「自分自身のルールで生きていけること」に近いと言えます。どちらの自立・自律にせよ、対義語としては「依存」と言えるのではないでしょうか。他人の目線や評価を気にすることなく、自分の意思判断で決められることが重要です。
じりつ(自立・自律)は社会人の条件
このように自立・自律して、個人主義やニヒリズムにとらわれず、社会のために役割を果たすことが社会人の条件と言えます。生活における自律(遅刻をしないなど)、経済的な自立(収入を得る)を果たし、他人の分まで責任を負えることが大事です。その観点から、家族観とも密接な関わりがあります。
家族観とキャリアオーナーシップ
キャリアオーナーシップは、職業選択やキャリアステップにおける選択のことだと思われがちです。しかし、キャリアというものが自分の過去を振り返った時の道であり軌跡と捉える場合、キャリアは仕事だけではなくその人の活動全てを指すとも言えます。
仕事後や休日の家族との過ごし方などの兼ね合いなど、1日24時間をどう使うのかという意味で考えれば、睡眠時間が8時間、仕事の時間が8時間、食事・入浴・自由行動が8時間と3分割すると、どのような時間の使い方をするかの決定はプライベートに関してもキャリアの一部とみなすことができると思います。
多重役割とキャリアオーナーシップ
また、家族ができた時にその親としての役割や、配偶者としての役割など、1人の人が持つ役割は多岐に渡ります。いずれかの役割に偏りすぎるのではなく、自分の人生としての位置づけや覚悟を持つことが大事です。
例えば、寿退社など結婚を理由に仕事を辞めてしまうことがあります。家族の状況に応じて専業主婦という生き方も選択肢としては必要です。一方で、本人の人生としての納得感があるかどうかについても疑問を持つ必要があります。家事や育児などで自分の時間が取れず、趣味やスキルアップなどの自己実現に時間を割くことができないことで、社会との断絶を感じることがあります。昨今では、女性の社会進出や女性活躍という文脈から子育てが終わってから再就職することを「社会復帰」と表現することもあります。家事や育児など家族の中での役割もありますが、自分の人生の生き方としてどんな時間を使い方をしたいのか、どうなりたくて、そのために何が必要なのかを考えることが大事です。
参考リンク:【キャリアデザインの教科書②】多様性と多重役割
多様化する家族観と「自立」
昨今では結婚をしない生き方もあります。結婚をしたとしても子どもをもうけないという家族観もあります。その個人的な生き方については他者が意見を言う権利もないし、聞く必要もないかと思います。
ただ、1つだけ注意をしなければいけないことがあります。それは「自立」というものがどういうものかということです。前述している通り、自立の定義を自分のことだけではなく、他人のことまで責任が持てるようになることだとすると、結婚をしてそれぞれが自由に過ごすことができるということは自立に至っていないということと同義になります。配偶者を支え支えられの関係になれていれば良いのですが、どちらかが依存関係にあるなど他人のことまで責任が持てるようになっていないこともあります。結婚をする必要とは何か、お付き合いをしているのと同じように自由なタイミングで別れることについての責任とは何かを考えなければいけません。
子どもと「自立・自律」
同様に子どもの有無についても自立に関係してきます。子どもがいる人は、強制的に子どもの責任を追うことになります。つまり嫌でも自立をせざるを得ない状況になります。子どもがいるにも関わらず自立しきれない人は、ネグレクトなどの事態に陥る危険性が高いです。
私自身も、子どもがいることによって仕事の時間が制限されたり、自分のプライベートな時間を持てなかったりと、自分の人生の軸とだけ考えれば自分の時間がなくなったと言えます。しかし経済的な自立と精神的な自律をしている証明として、子どもとの向き合い方があるように感じています。
自立した個人として社会を捉える
現在では経済的な視点や時間の効率など、個人単位で見ると結婚のメリットが感じられないことでしょう。個人だけの狭い範囲のメリットではなく、社会におけるお互い様の精神や長い目で見た時の社会構造のためには、自立した個人が必要です。
社会人とは自分の利益だけではなく、社会、他人のことまで責任が持てるようになることだと私は思います。



